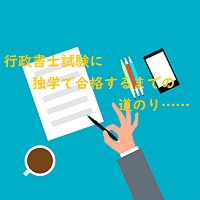継続は力でございます。そのためにはワクワク感が大事。
学び直しやリカレントにリスキリングなんて言葉が注目を集めていますが、勉強や学問というイメージと結び付けてしまうと固く苦しくなってきますよね。何を学べば良いんだ!?面倒だななんて感じてしまうとせっかくの機会を失いかねないためにもったいないと思います。今回は対象を決めて学び直し!?を始め、そして、継続するために大事にするとより効果が得られる8つのことを紹介します。わたし自身学生時代は学んでいる対象が将来何の役に立つのかあいまいな対象には情熱を感じることが出来ませんでした。しかし、働くようになってからというもの、その仕事で必要とされる能力を向上させ結果を得るために必要なスキルが明確な場合はそのたびにどん欲に吸収するように意識して取り組みました。いつの間にかそれが習慣となり50手前ですが毎日がエキサイティングでワクワクした時間を過ごしています。実は、ぜひ同じように学び続ける仲間が欲しいという思いもあってこのブログも続けています。
学び直しで老後の生活費問題も一気に解消
ネットのニュースや本屋さんに並ぶ雑誌の表紙に学び直しという文字が目立つようになり、最近では国会でも学び直しについて議論されていました。そこで、学び直しがなぜ必要なのか!?何のために学び直しをするのかという問題を自分なりに考えてみました。
学び直しが必要な理由
一番大きな問題と感じるのは、産業構造が変わり求められる職種も変化を迫られているからと考えています。スマホが登場し、情報の民主化が起こったと表現されますが、スマホの登場の前後ではあきらかに世の中の変化のスピードが違っていて加速化しています。この情報に触れ活用できるかできないかで人も組織も格差が生まれるというのは自然の成り行きだと思います。
このような社会を生きる以上、その情報のアップデートを理解できるくらいの学びは必要ではないでしょうか。ひじょうに抽象的ですが現在社会で相応の生活の質を維持しながら生きていくために学び続けることは必要だと考えています。
学び直しの恩恵
老後2000万円問題が何年か前に騒がれましたが。わたしが育った昭和の時代はサザエさん一家が標準的な家庭のイメージだったのかもしれません。当時は大体60歳で定年を迎え退職金で家のローンを完済してみたいな話だったと思いますが、今の時代にはほど当てはまらない部分もあるのではないでしょうか。年金の受給開始年齢の引き上げも一例ですね。さきほどスマホの話に触れましたがスマホの登場で価値観が多様化し、働き方だって多様化しました。この多様化はこれからもどんどん進むと思います。動画編集などはスマホひとつでもできる時代。新しい学びで得た知識で仕事を続ければさほど老後の資金を心配することもないように思うのです。そして、新しいことを学び実践することで新しい自分を表現できるという恩恵もついてきます。学び続けるということは本当に尊いですね。
何を学び直したいか、対象を見つける
すでに学びたい対象がはっきりしている人は問題ないのですが、学校を卒業して以来、勉強したことがなくて何を学びの対象にしたらいいのか見当がつかないという方もいらっしゃると思います。
学び直しの対象は興味を持つことができるもの
現在の仕事に関係することを選んだ方が良いという意見や、全く関係のないような対象を選択した方が良いという意見などさまざまありますが、それは意見を発した人の主観でありどちらでも良いと思います。なによりも大切なのは自分が興味を抱けるかどうがではないでしょうか。わたしの場合は過去に一度挫折未遂のある法律の学習がライフワークの一つになっています。もう一つ楽しみながら学んでいるのがWebマーケティングとPythonというプログラミング言語を使ったプログラムの学習です。なぜこのような構成になっているのかについてはのちほど紹介します。
学び直しの対象が見当つかず、興味を持つ対象も分からない場合の対処法
本屋さんに足を運びましょう。本なんて学生時代から読んだことがないという場合でも、この方法はおすすめです。本屋さんに行ったら本屋さんが進めているコーナーで並んでいる書籍の題名を眺めます。大体そこに並べてある書籍のテーマに思いを巡らすと今のトレンドが分かります。ネットでも本は見れますが、読書の習慣がない方であればネット検索の際にもキーワードが偏ってしまい有用な情報を逃してしまうこともあると思うので書店がおすすめです。わたしは完全に書店派です。暇があれば本屋さんに出かけます。宝さがしににた感覚でいつもまだ見ぬ情報との出会いにワクワクしています。
なかなか本屋さんに足を運ぶ時間的な余裕がないという場合には無料で学習できる動画サイトがありますので下のリンクから探してみてください。
学び直しの対象選択と同時に自分を客観視する
学び続けることはとても尊いことだと思いますし、読書もたのしくわたしはとても素敵な習慣だと思います。そのうえで、学び直しが少しでも稼ぎに影響するようなものであればなお良いと思うのです。学んだことが仕事に役立って仕事が以前よりも楽しくなった結果、成績や業績もあがり収入も上がったという好循環って理想的ではないでしょうか。もし、そうであれば学び直しで自分の周りの環境まで大返還というドラスティックなイメージよりも少しづつ積み増しするというイメージの方が学び直し前後の変化も比較的はやく感じることもできるはずなのでモチベーションの維持にも繋がります。
自分が楽しみながら学習できる対象かを意識する
学び直しには対象により時間を必要とするものもあります。わたしの法律の勉強などはけっこう時間がかかります。そこで自分自身が楽しめるかどうかという要素はとても大事だと思います。楽しくもないのにやらされている感でやる学習ほど身につかず苦しいことはありません。まさに苦行です。それでもそのスキルを得ることで収入が上がるといった事情がある場合には取り組むかもしれませんが、やはり自分が楽しめるか、ワクワクしながら向き合えるかというのはすごく大事な要素ですね。
学びっぱなしではなく実践(アウトプット)を意識する
本やネットで情報に接し、書いてあることを理解するというところで終わってしまって実際には身についていないというパターンもわたしのこれまでの反省としてあります。これは本当にもったいない。だから、この学習の定着度を上げるためにはアウトプットに重きをおく必要があると思います。
実際にはこのブログの記事だって学び直しや学び続けることの自分の考えに関するものでアウトプットの一種です。日ごろ思っていることを言語化することでより良いアイデアが急に浮かんできたりという幸運に出会うこともあります。また、このような記事に書かなくても自分の周りにいる人に話してみたりすることでも効果的です。わたしが取り組んでいる資格試験の先生が合格レベルの説明をされているときに、学んだことを説明できるようになったときとおっしゃっていました。自分だけ分かっていることを他人に分かりやすく説明するというスキルはひじょうに高レベルな能力が求められます。まさに先生の教えの通りだと思います。
自分のまわりの人に話すのも恥ずかしいような場合にはSNSで発信するというのも効果的だと思います。そんな私も家族に内緒でインスタもやっています。
学びをゲーム感覚で!!独学力を磨く
幼少のころから落ち着きのなかった私は今でもデスクにきちっと座って行う事務作業などが苦手です。勉強も同じようにきちんと座ってというのが今でも苦手です。最近は開き直って、そんな自分を受け入れるようにしています。学びというのを堅苦しくとらえると作法まで気になり肝心の学びの内容の理解が薄くなったり、モチベーションがそがれるなんてことになってしまうと本末転倒だからです。
そこで、最近では学びはゲーム感覚だと捉えています。昔熱中したドラクエなどのRPG(ロールプレイングゲーム)のようにやればやるほどレベルが上がっていく状態をイメージしています。そのためにレベルが上がったと感じたときには自分にご褒美ではないですがそんな要素も取り入れながら実践するのが楽しいです。そして、その結果として独学力を磨くというのをテーマにしています。独学は自主的に学ぶ姿勢が不可欠な要素としてあります。そして、独学であれスクールでの学習であれこの自主的に主体性をもって学ぶという姿勢の有無が学習効果に大きく影響すると考えているからです。その主体性を強化していくためにも独学力を高めたいと考えております。
自主的に学習対象の情報をアップデートする
続けてここでも自主的という言葉を使っていますが、能動的に対象に臨む姿勢で情報もどんどんアップデートする。アップデートといってもとくに何かをやるということでもなく、対象に自分から触れ続ける習慣を身に付けるということです。習慣を身に付けるといっても同じことを繰り返していれば自然と習慣化できるのでこれも心配ご無用です。
リベラルアーツ(一般教養)も同時に学ぶ
リベラルアーツというと興味のある目的に直結しなかったり、仕事の専門性を高めるものでもなかったりというイメージからどうしても後回しになりがちです。そんな一般教養をどうしてここでもちがしたかというと、結論的には自分で考える力を育てることができるようになるからだとわたしは考えています。
一般教養としては歴史や文化や宗教に倫理と多種多様な分野が控えていますが、実践を通じて学び続けるという手法であればさほど自分に負荷をかけることなく継続することができると考えています。そこで最近熱中しているのが食文化についてです。食文化を考える実践の場として自宅のベランダでプランターによる野菜の水耕栽培を始めました。人それぞれの意見はあると思いますが、わたしは何か新しいことを学ぶことに無駄はなく、普遍性の部分でのつながりはあると考えています。
社会人40代からの学び直し【まとめ】
- 何のために学び続けるのかを自分なりに明確にする
- 何を学びたいのか対象をみつける
- 学び直しの対象の選択と同時に自分自身を客観視する
- 学ぶ対象は自分が楽しめるものを選ぶ
- 学びっぱなしではもったいない。同時にアウトプットで学習効果倍増
- 学びを堅苦しく捉えずゲーム感覚で独学力を磨く
- 自主的に対象の情報をアップデートする
- リベラルアーツ(一般教養)を学び総合力を底上げする
さいごに、日本実業の父として尊敬している渋沢栄一先生が残された言葉に
四十、五十は洟垂れ小僧、
六十、七十は働き盛り、
九十になって迎えが来たら、
百まで待てと追い返せ。
というものがあります。激動の明治期で活躍した偉人らしい気概に満ちた言葉だと思います。渋沢先生からするとわたしはまだまだハナタレ小僧なんです。これは偉大な先達からのエールを頂いていると意気に感じで精進するしかありません。学び直しなんていうと年齢を気にする方もいらっしゃると思います。わたしもネット上の35歳限界説などという出所不明の言葉に軽くショックを受けたこともありました。しかし、今は学び続けることで変わり続ける自分を感じることができる日々でとてもワクワク充実しています。この記事を読んでいただいた方と別の機会に出会えることを願いつつこれからも学び続ける姿勢を大事にしたいと思います。